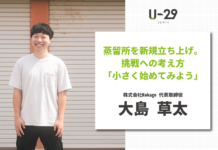社会的マイノリティーを撮影した写真展「糸しい」を開催

ーその後、17歳で写真展を開かれたそうですが、フィジーでの経験も関係しているのでしょうか?
そうですね。先ほどもお話したように、貧富の格差を目の当たりにして、社会課題にすごく敏感になっていた時期でもあって。何かできないかなと思っていたときに、コリア国際学園の友だちが、幼少期に受けた差別や偏見の話を思い出しました。
在日コリアンだけじゃなく、LGBTQやホームレス、障がい者やハンセン病回復者など、社会的マイノリティーといわれている人たちが、世の中にはたくさんいることが頭に浮かびました。
まずはそういう人たちのことを私が知りたいし、そのことを伝えていきたい。当時写真が好きだったので、写真で伝えていきたいなと思い、当事者たちの声や言葉と撮影した写真を展示した写真展を、京都・大阪・神戸の3ヵ所で開催しました。
資金はクラウドファンディングで調達して、 3ヵ所以外に幼稚園や高校などにもお声がけをいただきました。
ー当時17歳の高校生が写真展を開催しているって、すごいことですよね。インタビューをさせてもらう方とは、どうやってつながっていったのでしょうか?
写真展は、ユースACTプログラム(高校生が社会づくりの担い手としての自覚と自信を育むプログラム)の一環として行ったのですが、そこの代表の方に「こういう方を紹介していただけませんか?」両親に「こういう人を紹介してほしい」とお願いしていました。
周りの方につないでいってもらったなと感じています。この写真展が、自分の中での成功体験になっています。
写真展を終えてからも、写真展で出会った方同士が、一緒にイベントを企画されたり、来場者の中には、被写体のBIGISSUE(ホームレスの自立支援のための雑誌)の販売員の方から雑誌を今も購入し続けてくれている方がいます。
17歳の高校生の思いが、いろいろなつながりをもって広がっていく。そのつながりを今後も大切にしていきたいし、今後もそういうつながりを作れる人でありたいなと思っています。
ーその後は大学に進学されたのですよね?
はい。私は写真展など、活動することが好きだったんですよね。将来は社会問題を解決できるような人になりたいと思って、 社会起業家に憧れていた時期がありました。
慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパス(SFC)は、社会起業家を多く輩出されているところが魅力的でした。時間さえあれば学科の枠を越えて、総合政策学部や環境情報学部の授業を受講できる。ちょっと特殊な環境にあったので、SFCにある看護医療学部を選びました。
大学入学後は、夢だった途上国で活躍できるような助産師になるためには、何が必要かなと考えたときに、実際に現場に出て自分の目で見てみないといけないなと思って。
大学1年生のときに学生団体のAIESECに入り、夏にガーナ共和国のクリニックで、6週間のインターンシップをしたんです。
クリニックでは妊婦健診や初めてのお産、死産にも立ち会わせていただき、 将来はどういう助産師でありたいんだろうと考えるきっかけになりました。
海外からもたくさんの医療学生が来ていたので、学生同士の交流もおもしろかったし、すごく楽しかったです。
脳梗塞を発症し、生きる意味について考える

ーそこから18歳のタイミングで、 ライフログが急に下がっている時期があります。佐藤さんにどんなことがあったのか教えてください。
ガーナ共和国から帰国後、原因不明の発熱が続きました。ガーナと日本の両方で検査をしましたが、マラリアなどの感染症の検査をしても、全部陰性なんですよね。 原因がわからないまま、高熱と下痢だけが続いていました。
そのまま大学が始まって、解熱剤を飲みながら学校に通っていました。ある日、急に左手が全然使えなくなっていて。「なんでだろう?おかしいな」と思っていたら、意識を失って倒れていました。脳梗塞を発症していたんですよね。
今まで元気に過ごしていたので気付かなかったのですが、心臓の弁に問題がありました。そこに菌が住み着いていて、 血栓になって脳に飛んでいって脳梗塞になったようです。心臓の緊急手術を行い、1ヶ月の入院を経験しました。
その手術は本当に危険な手術で、 最悪の場合死ぬかもしれませんとか、植物状態になるかもしれませんとか、 散々リスクを言われて。すごく大変なことが起きているなと感じていました。
高校生のときは、写真展で被写体を引き受けてくれたハンセン病回復者の方からお話を聞いても「そういう差別や偏見を受けてこられたんだな」と、どこか他人事として捉えていました。しかし、自分が病気になったことで、初めて回復者の方々の気持ちを自分ごととして考えるようになったんです。
「私は病気になっても家族がサポートしてくれているけれど、回復者の方々は差別を受けて隔離されてしまい、どのような気持ちだったんだろう」と。
左半身に麻痺があり、障がいが残るかもしれないと言われていたので、このままずっと麻痺が残ってしまって、半身不随だったとしても私は生きていけるんだろうかと考えていましたね。
もし半身不随の私を受け入れられなかったら、今まで出会ってきた人たちのことを頭では理解していたかもしれないけれど、心では受け入れられていなかったんだなってことに気付かされました。
幸い手術はうまくいき、その後のリハビリで麻痺もほとんど残らず、不自由なく過ごせるように回復しましたが、人生で初めて死を身近に感じ、生きる意味について考えるようになりました。そこから、ハンセン病問題にもさらに取り組むようになります。
ー手術後は、どのように過ごされていたのでしょうか?
手術後は麻痺があったので、1ヶ月間は入院して、1年間はリハビリ期間として休学をし、実家で過ごしていました。
当時は、生きている意味がないんじゃないかとか、先も見えないしとか、すごく落ち込んで自暴自棄になっていました。
すごく苦しかったときに、視覚支援学校で、英語を教えていたアメリカ人の友人に、「アシスタントで芙優子も来てくれない?」と誘ってもらって。視覚支援学校のボランティアをさせていただきました。
そこで出会った子どもたちは、私と同じような境遇に置かれているけれど、すごく明るいんですよね。どんな状況であっても諦めずに、前を向いて歩んでいる姿を見て、私は逆に元気をもらったというか。
大きな気づきを得ましたし、その子たちとの出会いが支えになりました。
今までは活動をして、何かを成し遂げることに対して価値を見出していたんですよね。ところが病気になって立ち止まらざるを得なくなり、先が見えない、何もできない時期を経験したことで、その考えはだんだんと私の中で変わっていきました。
どんなに先の見えない大変な状況であっても、前を向いて1歩1歩歩んでいく中にこそ、本当の価値があるんじゃないかなと考えるようになったんです。
病気がきっかけで、今まで出会えていなかった人たちに出会えたり、価値観が180度変わったり、大きなターニングポイントでした。