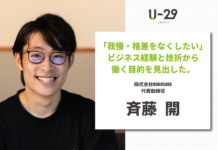様々なキャリアの人たちが集まって、これまでのステップや将来への展望などを語り合うユニークキャリアラウンジ。第519回目となる今回のゲストは、ナオライ株式会社で広報を担当する安田遥(やすだはるか)さんをゲストにお迎えし、現在のキャリアに至るまでの経緯を伺いました。
幼いころから地球環境問題に興味を抱き、これまで国内外問わずさまざまな持続可能な社会を目の当たりにしてきた彼女。「だれかのおかげで自分が生かされている状態が安心して暮らせる」と語る背景には、どのような人生を送ってきたのでしょうか。これまでの経験から今後の取り組みについて幅広く伺ってきました。
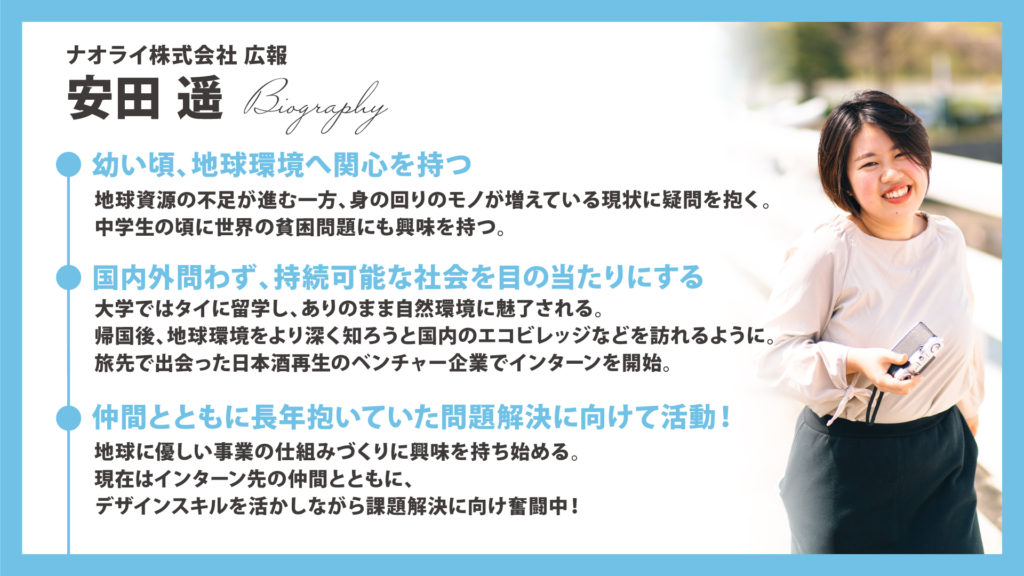
幼少期に芽生えた地球環境への関心

ーまずはじめに、自己紹介をお願いします。
青山学院大学地球社会共生学部に所属している安田遥と申します。現在は大学に通いながら、主にナオライ株式会社で広報を中心にインターン活動をしています。また、以前からグラフィックレコーディングの活動を個人で行なっており、これまでさまざまなイベントで実績を積んできました。
ー地球環境に興味を持たれている遥さん。幼少期はどのようなお子さんだったのでしょうか?
地球環境に興味を持ち始めたのは10歳の頃でした。地球資源の枯渇が予想されるこの世の中で、モノが増え続けている状態に疑問を抱きました。
例えば、昔は豆腐を買うとき、豆腐屋さんに鍋や器を持っていき購入しましたよね。でも最近だとプラスチックのパッケージに入れスーパーに陳列されている。便利だから、衛生的だからという理由で個装容器が全体的に目立ってきています。資源が限られているのであれば、そんな悠長なことはしていられないのではないかと不思議に思っていました。
この頃から、子どもながらに「みんなで力を合わせて資源を守れないのか」「将来の地球をどのように考えていくか」と感じていました。
ー興味のきっかけは小学生のときだったのですね。その後の学生時代はどうでしたか?
中学生の頃、社会科の先生が貧困問題に詳しい方で、よく貧困課題について教えてくれました。世界には教育を受けられない、十分に食事をとれない子どもがいるにもかかわらず、日本では不登校の学生や給食を残す生徒がいますよね。
そのときに、自分のいる日本の環境が世界にとっては当たり前ではないことを知り、わたしにできることがあれば積極的に取り組みたいと思ったのです。そして地球環境、貧困問題、そのような問題に対する解決策をさまざまなアプローチで学ぶことのできる青山学院大学地球社会共生学部に進学しました。
タイの山岳地域で見つけた憧れの環境

ー青山学院大学に入学してからはいかがでしたか?
大学に進学後、地球環境や世界の貧困について理解を深めようとしました。しかし「世界で活躍したい」「環境問題を解決したい」という思いが膨らむ一方で、行動が追いつかず精神的に苦しい状態に。そのときに、世界のためではなくまずは自分の周りへ貢献することから始めようと考えをシフトしたことで、徐々に精神的な余裕を持つことができました。
ーそのように考えを変えられたきっかけは何ですか?
自分自身がしんどいときに、だれかを助けようと気になれませんでした。そのとき初めて、自分が安定した状態でなければ、だれかのためになれないと気がついたのです。
そこで最初に始めたのがカメラとグラフィックレコーディング。シンプルに自分が好きなことは何だろうと考えた時に出てきたのが、この2つでした。グラフィックレコーディングでは、人同士の認識の違いを、絵を使って表現することに面白さを感じましたね。
ーご自身の安定した状態も取り戻すためにも、好きなことに取り組まれたのですね。
そうですね。あと、大学のプログラムでタイへ留学しました。留学の途中、タイ北部・チェンマイよりさらに上の地域を訪れ、山岳民族と出会う機会がありました。そこでは、国籍がない人が暮らしていたり、独自の民族語を話していたり、これまで自分が見たことのない世界でしたね。
ーそもそも、なぜ山岳地域を訪れたのでしょうか?
タイで出会った知人から「中野さん」という同じ大学の先輩が、現地でコーヒー農場を営んでいることを教えていただいたのがきっかけです。そこではコーヒー豆の作り方から加工の仕方を仕事として教え、さらには教育や住居まで提供するなど、まさに民族とともに生きていく活動をしてました。
支援っていうと、奨学金や本を送る一方的な関係がイメージされますが、中野さんは寄り添いながらサポートしていたのが印象的でした。
ーそこでの暮らしはいかがでしたか?
ほとんどすべてにおいて、周辺の環境で得られるものだけを使って生活していました。例えば、お昼ごはんの際には大きくて頑丈なバナナの葉をお皿として使っていたこと。イメージしていたプラスチックを使わない暮らし、資源や環境に配慮した暮らしをしている人たちの感覚を得られたことは、わたしの中では大きかったです。
持続可能な生活に安心感を抱く

ータイから帰ってきてからの活動について教えてください。
帰国後、コロナ禍で就職活動に挑みました。さまざまな会社を見るのは楽しかったのですが、仕事に対して求める条件を決定するためには検証が必要だと感じるように。そのために、大学を休学してフルタイムのインターンを始めました。
インターン期間中に、コロナが流行し始め、世界中が自粛した生活を送る一方、環境が改善されたというニュースを聞きました。例えば、わたしが留学したタイ・バンコクでは、車の渋滞がおさまり廃棄ガスが軽減。自粛した生活のおかげで、自然環境がきれいになったことを知りました。
ー自粛生活が、環境に大きな影響をもたらしたのですね!
今まで、環境を変えることが途方もない問題だと感じていましたが、今回のように世界中で力を合わせたら、実現できるかもしれないと思い始めました。そこから環境保全に配慮した社会を目指している「持続的な社会」に興味を抱き、国内の*エコビレッジなどを訪れるように。
*エコビレッジ:地域の持続可能性を目的とした暮らしを成立させるための社会づくりやコミュニティ団体
サステナブルな社会を目指して、運営の基盤がしっかりしている地域もあれば、環境問題解決と利便性を重視したいといったジレンマを抱えている地域もありました。
ーエコビレッジを訪れる中で、自分自身の大切にしたい価値観はありましたか?
そうですね。自分が安心して暮らせるための条件を大切にしていきました。旅の拠点の1つだった大崎下島(おおさきしもじま)と呼ばれる瀬戸内海に浮かぶ島の暮らしが印象的でしたね。その集落では、各家庭に小さな畑があり野菜を交換しながら暮らしています。また、トイレも汲み取り式のトイレを使用し、処理してくれる担当の人が存在していました。
「自分がだれかのおかげで生かされている」ことが分かる暮らしっていいなと感じ、その気持ちを抱きながら生活することが、安心して暮らせる条件だと気づきました。
ー話を聞く限り、地球環境に優しい暮らしだと感じました。その後、ナオライ株式会社のインターンをいつから始められたのですか?
はい。2020年12月より開始しました。弊社は主に、各地の酒蔵から買い取った日本酒を再加工して、”浄酎”というお酒を造っています。「低温浄溜」という技術で、日本酒をアルコールと水に分解し、まるでウイスキーのようなまろやかな味わいのお酒を生み出しています。
国内には1500ほどの日本酒の酒蔵が存在していますが、消費量は40年間で3分の1に減っている状況。そこで弊社が買い取ることで「再生酒」として販売、これまでの新酒を楽しむ文化から熟成を楽しむ文化に重きを置く、新たな領域で挑戦しています。
ー新しい和酒というわけですね!その中でも特にこだわっている点はありますか?
こだわりは、オーガニック食材です。弊社が酒蔵さんに日本酒を作っていただくときの酒米をオーガニック米に変更しています。オーガニック米でできた日本酒を、蒸留したお酒が売れれば売れるほど、そのオーガニック米の販路が増え、全国的に増える仕組みです。
チームのみんなで地球環境問題に取り組んで行く

ー仕組み作りがしっかりしていますね!遥さん自身のやりたいことに大きな影響を与えていますか?
そうですね。弊社は、環境に配慮した取り組みを常に実践的に行っています。今取り組んでいる活動が、長年抱いていた地球環境問題の解決へ意識を向け続けられることが有り難いと感じています。
一人で環境への意識を持ち続け、行動し続けるというのは、根気のいることです。ときには便利なものに流されたり、考えなしに消費することで楽になろうとするときもあります。しかし、現在組織として力を合わせ大きな仕組みを作っていくことや、自分たちで実践していこうとしている活動に安心感を感じています。
ー遥さんが、今後の活動をするうえで大切にしていきたいことは何ですか?
そうですね、時間のかかることに対してきちんと向き合っていくことです。例えば、オーガニックの田んぼを増やしていくことは時間がかかります。すぐに成果が出ないことは捨て、利益の出やすいことに参入する社会ですが、利益を生み出すことを考慮しつつ諦めないで取り組みを続けていきたいです。
それからデザインのスキルを活かしつつ、地球環境の課題解決に向けてなにか新しいことを取り組んでいきたいです。
ー最後に、U-29世代へメッセージをお願いします。
わたしはこれまで1つの軸に縛られず、複数の軸を持って行動してきました。本当の自分がやりたいことに迷ったこともありますが、あとから1つ1つの行動が繋がっているなと分かることもありました。軸を1つだけ持つというルールはないので、最後に自分自身が振り返ったときに納得したらいいのではないかと思います。
ー遥さんの挑戦を応援しています。本日はありがとうございました!
取材:松村ひかり (Instagram / Twitter)
執筆:田中のどか(Twitter)
デザイン:高橋りえ(Twitter)