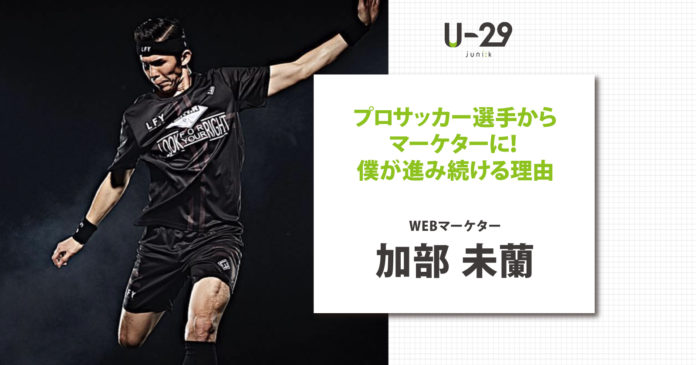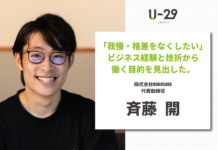様々なキャリアの人たちが集まって、これまでのステップや将来への展望などを語り合うユニークキャリアラウンジ。第544回目となる今回は、マーケターの加部未蘭さんをゲストにお迎えし、現在のキャリアに至るまでの経緯を伺いました。
プロサッカー選手からマーケターと、全く違う職種にキャリアチェンジした加部さん。キャリアチェンジの経緯や数々の転機について語っていただきました。

物心ついたときからサッカーは生活の一部だった

ーまずはじめに、簡単に自己紹介をお願いします。
加部と申します。私は元々、サッカーにルーツがあります。高校2年生のとき高校サッカー選手権大会で優勝し、その後プロサッカー選手として2年間活動しました。
今年の10月にウェルネス関連プロダクトをメインで制作している株式会社TENTIALに入社し、現在は商品開発のディレクションや新規商品の開発、リサーチ業務に携わっています。
ー17歳で高校サッカー選手権で優勝された加部さん。何がきっかけでサッカーを始められたのですか?
父がサッカーメインのスポーツライターなんです。子どもにサッカーをさせたい父親に、イタリアのプロサッカーチームにちなんだ「未蘭(みらん)」という名をもらってこの世に誕生しました。物心ついたときからサッカーボールを蹴っていて、サッカーは生活の一部だったんです。
それから小学生になって地元のクラブチームに所属し、中学生ではFC東京のジュニアユースに入って明確にプロを意識するようになりました。
ー中学校の部活ではなく、ジュニアユースに入った経緯を教えてください。
父のすすめもありましたが、小学校高学年になるにつれてサッカーで上にいきたいという思いが湧いてきたんです。様々なチームを見学し、最終的にFC東京のジュニアユースに入ることになりました。
ジュニアユースでは、学校に行きながら週5~6日サッカーの練習に打ち込む日々。部活に入っている同級生より遅い時間までサッカーの練習をしていました。その頃からプロになって活躍したいと思うようになりましたね。
ープレイヤーとして活動する中で、プロに対しての意識は持っていたのですか?
当時はまだまだ未熟でしたが、プロになることは意識していました。サッカーの試合には勝ちたいですし、練習だとしても目の前の相手には負けたくない。その思いを積み重ねてプロに近づいていったのかなと思います。
地元のクラブチームからJリーグチームの下部組織に入ることは、僕にとってプロへの第一歩でした。FC東京の方には今でも良くしていただいていて、ジュニアユースで監督やコーチ、チームメイトに出会えたことは本当にかけがえのないものだと感じています。
朝から晩までサッカー漬けの日々。“意識して努力すること”を身に付ける

ー素敵な出会いですね。高校へはどのように進まれたのですか?
僕は自分にとにかく甘かったので、厳しい環境に身を置くために強豪選手が多く入学する山梨学院高校に進学しました。
山梨学院のサッカー部は3学年合わせて100人以上。元々は山梨県内でもサッカー強豪校ではありませんでしたが、2学年上の代から強化を開始した高校でした。僕は入学当初から寮に住みはじめたため、中学生のときよりサッカー漬けの日々でしたね。
ー監督が大切にされていたことやチームの特徴など印象に残っているものはありますか?
特に印象に残っているのは、2年生のときに就任した吉永監督です。吉永監督は僕を信用してずっとスタメンに起用してくれて、僕の中で大切な出会いだったと感じています。
僕は中学生のときにFC東京のジュニアユースに在籍していたので、高校生になっても調子に乗っていたこともあって……(笑)。先輩に呼び出されて怒られたり、時にはケンカに近いこともしましたが、少しずつ人間としても成長できた時期でしたね。ちなみに、高校の先輩には今でも仲良くしてもらっています!
今まで意識して「努力」をしたことがなかったのですが、新しい環境に身を置くことでチームで勝利するための努力を意識的にできるようになりました。
ーサッカーをする中で上手くいかないときやつらいとき、心の支えになったものはありますか?
プロになりたいという思いもありますが、仲間がいることが一番心の支えでした。寮に帰ると同期の仲間がいて、同部屋には大親友がいて。監督にも相談しやすくどんなに苦しいことがあってもみんなで乗り越えていける環境だったので、全く心細くはなかったです。
また、朝の練習に遅刻すると坊主という罰則のおかげで朝が強くなりました(笑)。
ーサッカー選手権大会で優勝するまでの予選や決勝戦では、チームの雰囲気やご自身の感情はどのようなものだったのですか?
優勝を目指すというより、目の前の試合に全力を尽くして勝ち進んでいったら優勝していました。僕らはいつも通り試合に臨んでいたら舞台が大きくなり、準決勝・決勝戦では5万人もの観客がいて。
実は僕、全国大会のとき骨折していたんです。本当はドクターストップがかかっていたところを、無理を言って後半の20分だけ出場させてもらいました。
そのときは、本当に試合が終わってほしくなくて、現実離れしているというか……とにかくとても楽しかったのを覚えています。後半の20分だけでも信じて出場を認めてくれたヘッドコーチや監督、チームメイトには感謝してもしきれません。
高校サッカーとプロのギャップに苦戦。進学を決意する

ープロの道に進まれた加部さんですが、どのようにプロの道が拓かれたのでしょうか?
高校2年生のときに特別指定選手としてヴァンフォーレ甲府に迎え入れていただいて、練習に参加したり練習試合に出場したりさせていただきました。その頃からプロになると決めていたので、鼻高々に公言していましたね(笑)。
3年生の選手権が終わった次の日に代理人の方から「ヴァンフォーレ甲府からオファーがきました」と連絡をいただいたんです。それと同時に福岡大学からもオファーをいただいていて、進学とプロの道どちらに進むか非常に悩みました……。悩んだ末、友人からの「プロで活躍する姿をみたい」という声が決め手になり、プロの道を選びました。
ー実際にヴァンフォーレ甲府に入団されて、想像以上だったことや入ってみて気付いたことなどはありますか?
体格差やスピードなど、高校生とプロでのギャップの大きさには苦しみました。入団して3ヵ月くらいは、想像を絶するレベルの高さで全くついていけなかったんです……。
ギャップを感じつつも練習を続けて、練習試合などでは点を取れるようになり、5試合連続得点など自分としては結果を残していると感じていました。しかし、なかなか試合には出られなことが悔しくて、ジレンマを感じていました。
ープロサッカー選手から次のステップへ軸足を変えようと考えるようになった経緯や思いを教えてください。
僕自身はずっとプロで生きていくつもりでした。しかし、父がサッカー界に従事している人間というのもあり、1、2年試合に出られていないこの状況ではまずいと考えるように。そのとき父から「人間関係や一般常識を学ぶために一度大学に行きなさい」と進言され、大学進学に向けて動きはじめました。
選手としてまだこれからという時期にプロを辞めるのは非常に難しい選択でしたが、大学に進学してサッカー部に入部し、改めてサッカーを学び直して、プロを目指すべく再スタートを切りました。
社会人は「ビジネスアスリート」。全ての経験を基に社会貢献を続ける

ー在学中もう一度プロを目指した加部さん。なぜプロの道に進まず社会人の道に進まれたのでしょうか。
今までサッカーを続けてきたのは、お世話になった方々にプロとして活躍している姿を見せることで恩返ししたかったから。社会人になって仕事をしながら活躍している姿を見せることも恩返しの一つと考えて、社会人の道に進むことにしました。
ー社会人になる上で、業界や業種、職種はどのように選んだのでしょうか。
はじめは金融の会社にお声がけいただいて、その会社の方から助言をいただいたり、社会について教えていただいたりしました。その方から、まずは1年間営業経験を積んできてほしいとのことで、ITの会社に営業職として就職しました。
今でこそサッカーの経験が活かせると感じることもありますが、ITはサッカーとは全く違う世界で……。最初はサッカーの経験を仕事に活かそうと意気込んでいましたが、何もかもが違っていて難しかったですね。
ーサッカーと社会人のギャップに悩みながらも様々なことを吸収していったと思うのですが、今の会社と出会ったきっかけや入社を決意された経緯は何ですか?
TENTIALとのきっかけは転職エージェントからの紹介でしたが、代表の中西さんが話すビジョンに共感したこと、僕のマーケターの経験やリレーションを活かせる仕事だと感じて入社することになりました。
また、僕自身も身体のコンディションで困ったことや知らないことがあった経験から、人間の根幹であるヘルスケアやウェルネスに関わり、もっと世の中に貢献したいと思っています。
ー今後関わりたいことや実現したいことはありますか?
TENTIALはダイレクトに自分の経験を生かして社会貢献できる会社だと思うので、経験や知識をどんどん還元していきたいと思っています。商品開発に携わっているので、一人でも多くの人を幸せにできる商品を届けていきたいです。
僕たちは真摯かつハードにビジネスに取り組んでいる方を「ビジネスアスリート」と定義しています。そんなビジネスアスリートに商品を使っていただき、アスリートのようにビジネスに取り組めるコンディショニングをサポートしたい。自分もビジネスアスリートの一人として、これからもアスリートのように真摯にビジネスに取り組んでいきます。
ーありがとうございました!加部さんの今後のご活躍を応援しております!
取材者:山崎 貴大(Twitter)
執筆者:柚月 歩(note/Twitter)
デザイン:高橋りえ(Twitter)