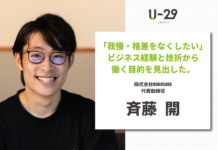東京を拠点に活動されている書家 小杉卓さん。大学卒業後、大手IT企業に就職するも、「書の可能性に挑戦したい」という思いから、フランスへ渡り、アートとしての書の制作を始められました。
現在、個展はもとより、フランスでのマツダのモーターショーやオーケストラが演奏するクラシック音楽に合わせた舞台での書道パフォーマンスなど、枠にとらわれない取り組みをされています。
そんな小杉さんに、渡仏しようと思った経緯、またアートとビジネスの関係について深く聞いていきたいと思います。
■ 原点は、子どものころ、褒められて伸びたこと

ーまず、小杉さんの学生時代から今に至るストーリーを簡単にご紹介していただけますか。
小杉:大学は国際基督教大学、ICUで、日本文学を専攻していました。大学2年生のときに東日本大震災のボランティアに行き、マイクロソフトの社員の方と一緒に活動させてもらう中で、今まで趣味で続けていた「書」というものを、もっといろんな形で展開できるんじゃないかと思いました。それが、「マイクロソフトと書」っていうキャリアのきっかけになりました。
でも、やっぱり大学を出てすぐ書道だけで食べていくってことは難しかったので、2013年にマイクロソフトに入社して3年半勤務しました。そのあと1年間パリに行ったのですが、その理由は、もともとフランスのアートがすごく好きだったので、その作品が生まれたパリで自分も制作活動をやってみたかったからなんですね。その後帰ってきて、東京で今2年目なので、独立してちょうど3年くらいです。
ー今はプロの書家として活躍されている小杉さんですけれど、そもそも書道との出会いとはいつ頃だったんですか?
小杉:実は、私の祖母が書道教室をやっていたんです。小学校に上がるタイミングで、私も生徒の一人として習い始めたのがきっかけでしたね。
祖母は褒めて伸ばすタイプで、ちょっとうまく書けただけでも、すごく褒めてくれたんです。誰かと比べるのではなく、以前の自分よりうまく書けているねと。それが自分が書道を好きになった一番の理由でした。今まで書道を嫌いにならずに続けられた原点は、そこにあったのかなと思います。
ーとはいえ、まだ書道の道には進まないと思っていたそうですね。では、小中高校で、賞を受賞したなどの成功体験はありましたか?
小杉:はい。書くことが好きで、それなりに入賞を重ねて高校の時は全国大会にも行きました。自分にとっての書道は、きれいに書いて入賞していくことだったので、その時はそれが僕の成功体験だと思ってたんです。でも、大学に入ってその考え方は変わりました。
■ 転換点は「誰かのために書く」「喜んでくれる人がいる」という体験

ーどんな時に、どういうふうに変わって行ったんですか?
小杉:それがまさに、震災の時のことで。その年の5月くらいに被災地に行かせてもらったんですが、家も家族も失った人たちを目の前にして、何も話しかけられなかった。そこでなんとなく、自分が今書道をやっているっていう話をした時に、ある被災者の方が、「せっかくだから、何か書いてもらえませんか」っていう話になったんですよ。それが、自分にとって初めて誰かのために書く書道だったんですよね。
ーエンターテイメントとしての書道、ですね。
小杉:そうですね、その時に一番悩んだのが、お手本がなかったことなんです。今までは書くものが決まっていて、入賞できる書き方が明確にわかっていた。だけど「書いてください」って頼まれた時に、何を書いたらその人が一番喜んでくれるのかっていうのが全く見えなかったんです。
たまたま、その方々が地域でお囃子をやっていて、それをすごく大事にされているのを目にしたんです。それで、お囃子のモチーフになっている「鹿」を一つの書の作品にして、次に行く時にお持ちしたんですよね。そうしたら「これは自分たちが考えた鹿そのものだ」ってすごく喜んでくれて。
書道って、それまでは賞をとったら自分が喜ぶものだったけど、誰かのために書いて誰かが喜んでくれるんだって、すごく揺さぶられました。書道でもっと書かなきゃいけないものがあるんだなとも強く感じました。
社会に対しての自分の考え方や、誰かが思っているけど言葉や形にできていないっていう状況を「書」を解決策として、僕にできることがあるんじゃないかと思い始めたんです。
ーそこからどんなふうに活動が変わっていったんですか?
小杉:その時すぐ、作品が仕事になったわけではありませんでした。でも、ふと周りを見た時に気づくようになったんです。例えば12月だと、ハロウィンが終わって、クリスマスとイルミネーションの季節になるわけですが、実はこの1ヵ月の中には、二十四節季という、もっと細かい季節があるんです。いまは小雪、大雪、もうすぐで冬至が来るっていうふうに。
自分たちが無意識に過ごしている季節も、毎日変わっているんだな、社会の変化の中で、今僕たちってどういう言葉を書かなきゃいけないんだろうなっていうところに目が向くようになりました。
そこで少しずつ、フェイスブックやホームページに作品を載せていったんですよ。そこから依頼が増えだして、これが仕事になるのかもしれないっていうのを大学最後の2年間で感じました。
ー何か大きな機会があったわけではなく、小さな出来事の積み重ねがきっかけだったということですね。いつかはプロになるぞという気持ちが芽生え始めたのは学生時代ですか?
小杉:そうですね。自分が表現をしたいと思った時に、パリコレという舞台でパフォーマンスをしたり、デザインとしての書を発表したりしたいなって、漠然と浮かんだんですよ。
でもそこまでのプロセスは全然見えてなくて。その一方で、ボランティアを通して出会ったマイクロソフトという会社に魅力を感じていたので、まずそこで働いてみようって思いました。
■ マイクロソフトで刺激を得て、書家の道を選んだ

ーいつかは、書家として、パリコレで自分の言葉をあしらった服が歩いているっていう状態をと、夢見ていたんですね。でも一旦は就職しようと思ったわけですが、マイクロソフトに決めたきっかけはなんだったんですか?
小杉:2つ大きな理由があって、一つは、ITの可能性を感じた部分です。自分の出身が栃木の田舎なんですけど、そこをITで変えられるかもしれないっていう。
もう一つは社員の人たちです。ボランティアってすごくエネルギーがいるんですけど、マイクロソフトの方はすごかったですね。ITが社会を変えるって確信を持ってやっていたと思うし、マイクロソフトで出会った方々が、自分のパッションの中で仕事を作っていたっていうことに魅力を感じました。
ーそのあと、2013年にマイクロソフトさんに入社されたのですが、社員の方の魅力についてはどうでしたか?
小杉:入社してからも、やっぱりすごい人はたくさんいました。そういう中で「自分はどうしたいのか」っていうのを強く考え始めるようになりましたね。
ー1年間はITコンサルタント、そのあと2年間セールスと、3年間マイクロソフトにいらっしゃったわけですよね。その3年間の中で、成功体験はありましたか?
小杉: 僕は失敗体験しかなかったように感じていたんですが、それはもっと書道に時間をかけたいという理由があったからなんですよね。このままでいいのか、今「書」を全力やらないでいいのかという思いが、じわじわと溜まっていて辛かった。
そして4年目、 26,7歳になった時に、まだ20代なら書がだめでも再就職できるぞと。
ー今なら独立できるという自信があって独立したわけではないんですね。
小杉 :はい。書道の仕事が増えていたとはいえ、絶対的な自信があったわけではなかった。収入も、マイクロソフトに勤めていた方が3倍くらい多いし、だけど今やらなかったら、書道が広がっていく可能性が少なくなっちゃうなと思ったんです。だからその時に、リスクを取るっていう選択をできたことは、良かったですね。
ーそういう意味では、副業が可能なマイクロソフトでよかったかもしれないですよね。会社の方の理解はあったんですか?
小杉:はい、上司の後押しもすごくありました。自分の心の中にやりたいことがあるんだったら、それをやったほうが絶対いいっていうアドバイスをくださって、すごくありがたかったですね。ただ、業務の中で大きな貢献をできなかったことが自分の中ではすごく心残りだった。だからこそ、今やらなきゃ、と思っています。
■ パリで、アートとしての書を確立したい

ー辞めて選んだ道を成功にしていかないと、と思っているわけですね。そこから2017年にマイクロソフトを辞めて、半年後にパリにいくわけですが、実際に行ってみてどうでした?
小杉:感じたことは2つありました。一つは、「いけるな」っていう可能性からくる自信と、もう一つはまだまだ時間がかかるっていう現実的な部分。
今、アニメの影響とかで、日本ってすごくフォーカスされてるんですよね。ラーメン屋さんもめちゃくちゃ増えてて、行列ができてるんです。そういう日本ブームの流れの一環で、書も興味を持たれることは多かったんですよ。でも、「日本的なもの」というふうに書がみられているうちは、書の価値って伝わってないんだろうなと。正直、本質的な書が全体に広がるのは時間がかかるっていうのを感じた部分がある。
一方で、アートや表現に対しての寛容さが違うところに、可能性を感じたんですよね。表現をする人への態度やリスペクトも全然違う。自分が何者で、何をしに来たのかっていうのをよく問われるんで、何十回も何百回も話しました。
それは日本だからとか書道だからとかではなくて、何かを感じようとしてくれる人が必ずいる。だからこそアートの文化が育ったんだろうなって思いました。そこで、伝えられる部分が確実にあったので、フランスでもっとやりたいとも思いましたし、東京でもきっとできるっていう自信にもなりました。
■ みんなが持っている「書」のフレームを壊したい


ー日本に戻られてから、少しずつお仕事いただけていたとはいえ、書家として営業も行うのは難しいと思います。どんなふうに仕事を取っていったんですか?
小杉:パリのときから、営業はずっとしています。パリには知り合いはゼロで、最初2、3ヵ月は仕事もゼロだったんですよ。行く前に、紹介してもらった人のリストを作っていたんですが、毎日人に会って、こういう作品書いてて、こういうことがやりたいんですって、ずっと言い続けて。ようやく書道を教えてほしいとか、イベントがあるからパフォーマンスしてみないとか、少しずつ仕事をいただけるようになりました。
今もそうなんですけど、例えばワークショップに来てくださった方から依頼を受けた時に、一回、その方の期待値を超えるものを用意したいっていうのがあって。
書道って、日本のほぼすべての方が体験しているがゆえに、すでに一つのフレームができていると思うんですよ。だけど、僕はもっとフレームは広い、なんだったらフレームはないって思ってるので、ファーストアタックの時にどれだけそのフレームを壊せるかだと思っています。そうなった時に、何かが生まれるなと思ってます。
ー書に対するフレームを壊すことで、アイデアを膨らますということですね。では、フレームを壊すためにどんなことをしていらっしゃいますか?
小杉:自分の中で変えちゃいけないところと、変わり続けなきゃいけないところを明確に分けています。変えちゃいけないところは、僕は書って言葉の表現の芸術だと思っているんで、それだけは書道の中でずらせないんですよね。
だけど一方で、言葉をどう表現するかっていう部分には線を設けたくない。例えば筆や紙、墨を使わなきゃいけないだとか、逆に色を使っちゃいけないとかっていうことを、僕は表現においては絶対考えたくない、と思っています。
誰かと話している時に、その人にとって一番いい表現はなんなのかっていうのは、いつもゼロから考えたいなと思っています。それが結果として、その方が持っている書のフレームとは全然違うところにいけるんじゃないかなと。だから言葉を描くっていうのは、書の真ん中にあるものだと思うんですけど、その周りの部分のフレームってあるようで何もなかったみたいなところに、ハッとしてもらえたらうれしいと思います。
ーそういうところから、気づきを書に表しましょうというワークショップをされたりしたんですね。マツダの発表会でも書を披露されてましたが、書家としての成功体験は、何かありますか。
小杉:そうですね。それはある特定のお仕事ではなくて、マツダも含めてですが、大きな舞台で人前で披露するっていうことに、大きな可能性があると思いました。
去年から、クラシック音楽と一緒に舞台を作ってるんですけど、ライブでショーを見てもらう、というのは自分の取り組み方を変えてくれたと思っています。
なぜならば、より共通体験としての書を提供できるなと思って。言葉って、もっと自分の内側から湧いてくるものだったりとか、それに触れて相手も新しい言葉が生まれてきたりとか、もっともっとライブなものだと思うんです。そのライブで書を披露するにあたって、書には時間があるっていうことを僕は気づいたんです。絵画と違って、書は、どこから書き始めてどこで書き終わるかっていうのがわかるわけですよ。そこに始まりと終わりがあるということは、そこの間の時間が存在するってことなんですよね。目の前でライブで書いていたら、なおさら、その字を書き終わっていく時間を共有できる。ということは、より深く言葉を生で感じてもらえているってことだと思うんですよね。そういう表現をこれからもっともっとやっていきたいと思っています。
■ アートとビジネスの刺激しあえる関係とは

ーアートとビジネスは分断されたものじゃなくて、アートにおける思考法っていうのはビジネスにいける、だからビジネスパーソンこそアートを学ぶべきだ、みたいな考えがあると思うんですけど、それに関して小杉さんはどう思いますか?
小杉:そこはすごく興味深いなと思っています。山口 周さんの本も何冊か読みましたし。そもそも人間が人間らしくいきていくためには、自分が頭で考えたことを、自分で決めないと幸せにはなれないと思っています。それをアート思考って言い換えているのかな。
例えば、ビジネスで数字的な答えって出せますよね。どういうデータをどういうふうに使うかっていうのは考えなきゃいけないけど。でもアートって自分の中から出さないと出てこない。そこにはどういう色をどういう割合で使ってとか、筆をどういう筆圧で入れるとか、すべて考えて出されているものだと思うんですよね。
むしろ、僕はアートの方にビジネスを持っていったら面白いと思っています。私たちみたいなアートに関わってる人こそ、ビジネスとして、お金や興味がどう動いているのかにもっと目を向けないと、表現って出てこないと思うし。お互いが刺激しあえる部分は、たくさんある気がします。そういう意味でのアートとビジネスの関係性っていうのはすごく考えています。
ー実際にマイクロソフトで働いていたからこそ、書家としてできたこともたくさんあるかと思うんですけど、例えばどんなことが生きたと思いますか?
小杉:ビジネスってお客さんがいることが大前提じゃないですか。それが今の自分の中でとても助けられている部分です。
僕は、書は究極のアートでありデザインでもあると思っているんですけど、何を、誰に、どう伝えたいのかを常に意識しなきゃいけない。それは究極的にはビジネスも一緒だと思っていて。この商品を、誰に、どういうふうに使って欲しいか、その答えを導いていくプロセスっていうのは全く同じだと思います。それを、マイクロソフトで猛烈に体験できてよかったです。
■ アートを言語化することで感性を磨く

ービジネスでも、フレームにハマった提案でなく、その人の独自性とか、感性を入れると面白い提案になることがあります。感性を磨く時間がないというビジネスマンのために、もっと仕事に生きるような感性を磨ける方法があれば聞きたいなと思います。
小杉:私は感性って究極の論理だと思っています。アーティストって、よく感性で書いてるとか、演奏してるって思われることがあるけど、少なくとも私はそうじゃなくて。紙の墨の吸い方はこれくらいだからこのくらいのスピードで筆を動かさなきゃいけないというように、すべて何かのロジック、論理を元に書いています。
ただ感性を磨きたいっていっても、つかみどころがなさすぎちゃう。音楽を聴く時も、感性で聴くってどうやって聴くんだろう、みたいな。でも、例えばこれって気持ち良さ数100あるうちの、95くらい気持ちいいんですとか、それってこういう理由があるんですって言った時に初めて、なるほどなって共感してくれると思うんですよね。そういうふうに、感性を数字で見る、言語化してみるっていうのはすごく大事なことだと思ってます
だから、何か「あ、いいな」と思ったものを、きちんと言葉で説明してみることですね。いい音楽だなと思った時に、どういい音楽なのか。この音がすごく好きだと思ったら、どんな和音でできているのかを仕組みまで見ようとする。すると、きちんと理由や裏付けのある感性になるし、自分の感性はそういうものに響きやすいっていう自己認識にもなると思うんですよ。そうなった時に、それは武器になると思います。
ー感性っていうのは言語化してロジックに落として見ると、磨かれていく部分があるということなんですね。
小杉:そうだと思います。
■ これからは、社会にたいして「書」でできることをやりたい

ー最後にお伺いしたいのは、これから小杉さんが書家として、また書家という役割を超えてチャレンジしていきたいことはどんなことでしょうか。
小杉:もちろんパリコレを目指すっていうのはあるんですけれど、ここ1年で、社会に対して書で何ができるのかというのをすごく考えるようになって。
モデルにしてる考え方が、ベネズエラの「エル・システマ」っていうプロジェクトなんです。何十年か前に、ベネズエラで子供の貧困がすごく問題になったんですが、それを政府がクラシック音楽教育でなんとかしようとしたんですよ。
貧しくて教育も受けられないような子に、ただでクラリネットとかフルートとか楽器を配って音楽教育を始めたんですよ。音楽って一人でもできるけど、みんなで合わせることの楽しさも教えたんですね。面白いですよね。
今、そのベネズエラで音楽教育を受けた人が、ベルリン・フィルとか、世界のトップオケといわれるところで活躍する音楽家になって、どんどん輩出されているんですよ。そういうふうに、音楽で一つの社会問題を解決できることって、すごく面白いし、アートってそうあるべきだなって思ったんですよね。
これからの時代に起こりうる社会問題ってたくさんある。そして、書っていうものは日常から、だんだん離れていってしまっている。では社会と書はどんな関わり方をしたらよいか、例えば教育の中で書と関わっていったら、社会がどう前進するかとか考えています。これは中長期的に取り組んでいきたいなと思っています。